netstatの後継コマンド「ss」とは?名前の由来を解説
netstatの後継コマンド「ss」とは?名前の由来を解説
はじめに
Linuxでネットワーク接続の状態を確認する際に使われてきた netstat コマンドですが、現在では ss コマンドが主流になりつつあります。
では、ss という短い名前にはどんな意味があるのでしょうか?この記事では、その由来と背景を詳しく解説します。
ssコマンドとは?
ss コマンドは「socket statistics」の略で、TCPやUDPなどのソケット状態を表示するためのツールです。
netstat の後継として iproute2 パッケージに含まれており、より高速・高機能なツールとして開発されました。
主な用途は以下の通りです:
- TCP/UDPソケットの一覧表示
- LISTEN状態のポート確認
- 接続状態ごとのフィルタリング
ssは何の略か?
ss はその名の通り socket statistics の略です。Linuxカーネルが持つソケット情報を高速に取得・表示することを目的として開発されました。
ss は /proc/net 以下の情報を直接参照するため、netstat よりも動作が速く、詳細な情報を取得できます。
netstatからssへの移行が進む理由
従来の netstat に比べ、ss には以下のようなメリットがあります:
- 高速な表示性能:データ取得が迅速
- 保守性:
net-toolsパッケージは非推奨 - 多機能:フィルタや統計表示が豊富
まとめ
ss コマンドは「socket statistics」の略で、netstat に代わるネットワーク調査の新定番です。
Linux環境でのネットワークトラブルシュートや状態監視には、今後ますます欠かせない存在となっていくでしょう。
まだ使ったことがない方は、ぜひ ss を試してみてください。
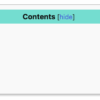
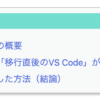




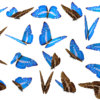

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません